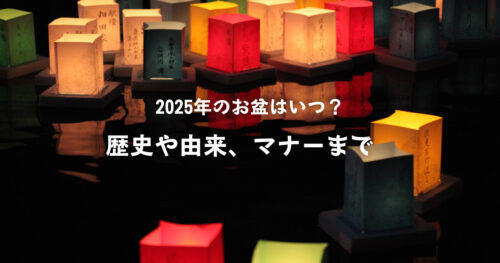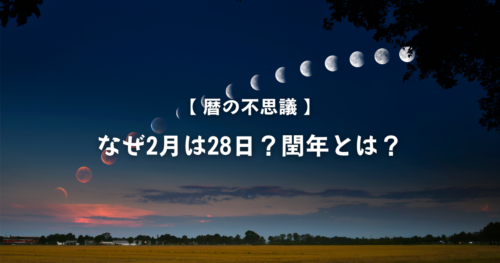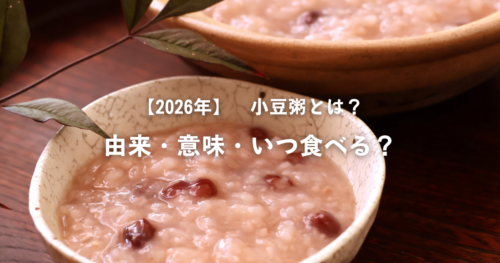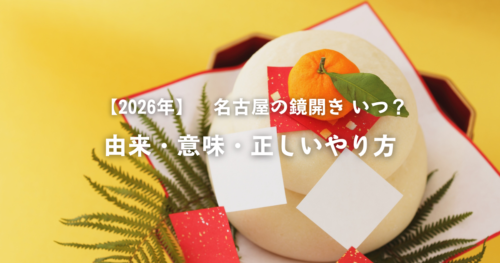8月15日。終戦から80年を迎えるこの日、私たちは命の重さと平和の尊さを改めて心に刻みます。
名古屋に目を向けると、8月15日は愛知縣護國神社の献水祭が恒例行事です。戦場での渇きを訴えて命を落とした英霊に供物として水を捧げ、正午には大太鼓の音とともに黙祷が捧げられます。地元住民をはじめ遺族・参拝者が集い、「命への感謝」と「平和への願い」を静かに祈る時間です。
また、名古屋市が主催し5月14日に開催される「なごや平和祈念式典」も、空襲被害や戦争体験を後世に伝える重要な取り組みです。この式典では、体験者による語り部や学生有志による平和宣言、市民が制作する啓発動画の上映といった企画が展開され、名古屋独自の「平和を形にする式典」として注目されています。
終戦記念日の意義と歴史的背景
1945年(昭和20年)8月15日、日本は太平洋戦争(第二次世界大戦)の終結を迎えました。この日正午、昭和天皇による玉音放送により、ポツダム宣言の受諾が国民に報告され、「堪え難きを堪え、忍び難きを忍びて…」という天皇の肉声が全国に届けられました。この放送は、日本人が降伏を肌で感じた瞬間でもあり、終戦記念日が8月15日とされる所以です。
ちなみに、海外では多くの国が9月2日の降伏文書調印をもって戦争終結と位置づけています。
全国戦没者追悼式と法的整備
1963年(昭和38年)から、毎年8月15日に政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開催。天皇・皇后、首相をはじめ各界の代表、市町村長や遺族代表が参列し、正午から1分間の黙祷、献花が行われます。
1982年(昭和57年)には閣議決定で8月15日が「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と正式に決定。以来、学校や公共施設でも黙祷や式典が行われ、平和への願いを新たにする日として位置づけられています。
名古屋における終戦記念日の行事
愛知県護国神社「献水祭」
名古屋市では、8月15日に愛知県護国神社で開催される「献水祭」が知られています。午前10時30分から行われるこの儀式では、参拝者が英霊に水を捧げ、戦場での渇き苦しんだ戦没者を慰霊します。その後、正午には本殿で黙祷・玉音放送視聴が行われます。
境内には戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦没者約9万3千柱が祀られ、慰霊碑や太玉串など歴史を感じさせる設備が整えられています。例年、地元住民だけでなく県内外から多くの参拝者が訪れます。
| 名称 | 愛知県護国神社 |
| 所在地 | 名古屋市中区三の丸1丁目7−3 |
| URL | https://www.aichi-gokoku.or.jp/ |