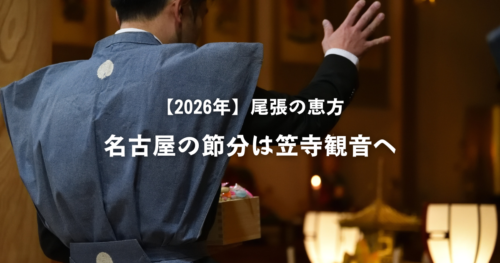愛知県知立市に鎮座する知立神社は、古くから「三河国の二宮」として信仰を集める由緒ある神社です。東海道五十三次39番目の宿場町・池鯉鮒宿(ちりゅうじゅく)の総鎮守として栄え、交通安全・厄除けのご利益で知られています。
毎年5月に行われる「知立まつり」では、豪華な山車と伝統的なからくり人形芝居が奉納され、多くの参拝者でにぎわいます。そして、初夏には神社に隣接する知立公園の花菖蒲が見頃を迎え、「知立公園花しょうぶまつり」が5月11日~6月8日まで開催されます。明治天皇ならびに昭憲皇太后御遺愛の名品60種の花菖蒲が咲き誇る光景は圧巻で、全国から多くの観光客が訪れる名所となっています。
知立神社とは
アクセス


🚗 車でのアクセス
・名古屋方面から:名古屋第二環状自動車道「豊明IC」から約15分
・岡崎方面から:伊勢湾岸自動車道「豊田南IC」から約10分
🅿 駐車場情報
・知立神社には無料駐車場があります。(台数に限りあり)
・混雑時は、周辺のコインパーキングを利用するのがおすすめです。
🚆 公共交通機関でのアクセス
・名鉄名古屋本線・三河線「知立駅」下車、西口より徒歩約10分
・「名鉄名古屋駅」から特急・急行で約20分
歴史的背景や由縁など


知立神社は、三河国の二宮として古くから崇敬を集める由緒ある神社です。創建は不詳ですが、弥生時代の景行天皇期から祀られていたとされ、平安時代にはすでに格式の高い神社として記録に残っています。
御祭神は、鸕鷀草葺不合尊はじめとする四柱の神々で、国家安寧・家内安全のご利益があるとされています。特に、江戸時代には東海道の宿場町「池鯉鮒宿」の総鎮守として栄え、多くの旅人や武士が参拝しました。
また、知立神社は「池鯉鮒大明神」とも称され、かつてこの地が池鯉鮒と呼ばれていたことに由来します。これは、境内近くに池があり、そこに生息していた鯉や鮒にちなんで名付けられたと言われています。


江戸時代には、知立神社は東海道三社(三嶋大社・熱田神宮・知立神社)の一つとして広く信仰され、多くの旅人が道中の安全を祈願する場所でした。また、徳川家からも篤く信仰され、社殿の造営や祭礼の保護を受けました。
現在でも、毎年5月に開催される「知立まつり」では、豪華な山車が巡行し、伝統的な「からくり人形芝居」が奉納されるなど、歴史と文化が息づいています。
知立神社は、長い歴史を通じて地域の人々に愛され続ける神社であり、今も多くの参拝者が訪れるパワースポットとして知られています。


🔹 お万の方ゆかりの地
知立神社は、徳川家康の側室であるお万の方と深い関わりを持つ神社です。お万の方は、知立神社の神主家の出身であり、その子である永見貞愛は、知立神社の神主を務めました。お万の方は徳川家の子を産み、その血筋は江戸幕府の要職にもつながるなど、歴史的に重要な人物です。知立神社を訪れた際は、こうした徳川家との縁にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
🏛 養正館 – 明治時代の貴重な建築
知立神社の境内には、明治時代の貴重な建築物である養正館があります。明治19年(1886年)に明治用水連合水利土功会の事務所として建てられ、当時としては珍しい洋風建築が採用されました。さらに、明治23年(1890年)には陸海軍大演習の際に明治天皇の御休憩所となったため、「記念館」とも呼ばれています。現在もその歴史的価値から保存されており、当時の趣を感じられるスポットとして人気です。
📜 松尾芭蕉の句碑 – 俳聖が詠んだ知立の風景
知立神社がある知立の地は、かつて東海道の宿場町「知立宿(池鯉鮒宿)」として栄えました。俳聖・松尾芭蕉もこの地を訪れ、「不断たつ 池鯉鮒の宿の 木綿市」という句を詠んでいます。この句碑は、池鯉鮒出身の芭蕉門人井村祖風によって建てられました。知立宿のにぎわいを今に伝えるこの句碑は、俳句や歴史好きの方にとって必見のスポットです。
知立神社の概要
| 名称 | 知立神社 |
| 所在地 | 愛知県知立市西町神田12 |
| 御祭神 | 鸕鷀草葺不合尊、彦火火出見尊、玉依比売命、神日本磐餘彦命 |
| 創建 | 景行天皇の頃 |
| URL | https://chiryu-jinja.com/ |